毎日「疲れた」が口ぐせになっていませんか?
「もう疲れた…」
気がつけば、この言葉が口から自然と出ていませんか?
朝はバタバタ、仕事では気を張り、帰宅後はノンストップの家事と育児。
ようやく子どもが寝たと思ったら、洗濯物が山積み。気づけば夜中にスマホ片手に寝落ち…。
そんな日々を繰り返していれば、「疲れた」が合言葉になるのも当然です。
でも大丈夫。
この記事では、乳児から小学生までの3人育児中の ワーママである私が実践している、
- 即効性のあるリフレッシュ方法
- 自己肯定感を取り戻す考え方
- 夫婦の協力や働き方の工夫 など、
ワーママの「もう限界。疲れた…」から抜け出すためのヒントをまるっとお届けします。
「私だけじゃないんだ」と思える共感と、
「これならできるかも」と思える小さな工夫を、ぜひ持ち帰ってくださいね。
第1章:即効でラクになる!疲れリセット法(短期ケア)
朝日を浴びて「幸せホルモン」をチャージ
朝のカーテンをさっと開けて光を浴びるだけ。たったこれだけで、体と心が少し軽くなります。
人の体は、太陽の光を浴びると「セロトニン」という神経伝達物質を分泌します。
セロトニンは別名「幸せホルモン」と呼ばれ、気分を安定させたり、自律神経のバランスを整える効果があることがわかっています。
さらに、朝にしっかり光を浴びることで、夜には眠気を誘う「メラトニン」が分泌されやすくなり、睡眠の質も良くなると言われています。
つまり「朝の光=その日の快調なスタート+夜の安眠の準備」になるのです。
ポイントは「短時間でも毎日続けること」。
ベランダで子どもと一緒に深呼吸する、保育園に行く道を少し遠回りして歩いてみるなど、生活の一部に取り込めば無理なく続けられます。
「今日は気持ちが沈んでるな」という日ほど、意識してカーテンを開けてみてくださいね。

「ながらストレッチ」で気分転換
「あ〜疲れた」が口癖のママたち。
疲れの正体は、体のコリや血流の滞りから来ていることも多いのです。
「運動しなきゃ」と思っても、わざわざ運動する時間を作るのは難しいですよね。
そんなときにおすすめなのが「ながらストレッチ」。
- 料理をしながら → つま先立ちでかかとの上げ下げ
- 洗濯物を干しながら → 両腕を大きく回す
- 子どもと遊びながら → しゃがんだり立ったりのスクワット風動作
こうした簡単な動きを生活の中に取り入れるだけで、筋肉がほぐれて血行が促進されます。
血流がよくなると酸素が全身に届きやすくなり、頭が重い感じやだるさ・肩こりも和らぎますよ。
また、体を動かすことで「エンドルフィン」という快楽ホルモンが分泌され、自然と気分も前向きになります。
「よし、ストレッチするぞ!」と気合を入れなくても大丈夫。
「ついでに動かしてみよう」くらいの気軽さで、リフレッシュしていきましょう。
5分のおやつタイムで脳を休める
ママが疲れを感じる大きな理由のひとつは「脳のオーバーヒート」です。
仕事・家事・育児とマルチタスクを続けていると、脳がフル回転しっぱなしでエネルギー不足に。
そんなときこそ「おやつタイム」!
糖分を少し摂取することで脳のエネルギー源であるブドウ糖が補給され、思考力や集中力が回復します。
おすすめは、
- チョコレートやドライフルーツ(素早くエネルギー補給)
- ナッツ(ビタミンB群で疲労回復をサポート)
- ハーブティーやカフェインレスコーヒー(気持ちをリセット)
ポイントは「5分でもいいから、自分のために座って味わうこと」。
立ったまま流し込むのではなく、好きなマグカップを使ったり、ちょっと香りのいい紅茶をいれたり。
小さな工夫で「自分だけの時間」を楽しむと、イライラや疲れでやさぐれた心も潤います。
おやつは罪悪感ではなく、ママの心を回復させる大事なスイッチ。
どうぞ堂々と楽しんでください。
🎁私の最推しスイーツ。何度もリピートしてます。自分へのご褒美としてぜひ!
足裏マッサージで「全身リラックス」
実は「疲れたなぁ」と思ったとき、足の裏をもむだけで体全体が軽くなることがあります。
足裏には「反射区」と呼ばれるツボが集まっていて、そこを刺激すると体の各器官や自律神経に働きかける効果があるといわれています。
特におすすめはこの3か所:
- 土踏まず → 消化器系を活性化。自律神経のバランスを整えやすい
- くるぶしの内側 → むくみに効果的
- 足の指や指のつけ根 →頭、 肩こりや目の疲れに
方法は簡単。
親指でゆっくり押したり、ゴルフボールや青竹踏みをコロコロ転がすだけ。
お風呂上がりにクリームを塗りながらマッサージすれば、血行がさらに良くなり、冷えやむくみ解消にもつながります。
(消化不良になる場合があるので、足裏マッサージは食後1時間すぎてからにしましょう)
「今日もよく頑張ったね」と自分に声をかけながら行うと、心もじんわり温まりますよ。
第2章:自己肯定感を高める考え方(中期ケア)
「完璧じゃなくていい」と自分を許す
「ちゃんとしたご飯を作らなきゃ」
「宿題も見てあげなきゃ」
“母親なら当然”と、無意識にハードルを上げていませんか?
仕事でも家庭でも全力投球してしまい、気づいたらヘトヘト…という悪循環に陥りがちです。
でも本当は、「100点のママ」でなくてもいいんです。
イギリスの小児科医であり精神分析家であるウィニコットは、
「グッドイナフ・マザー(ほどよい母親)」
という考え方を提唱しました。
完璧な母親ではなく、“ほどほどにいい母親”の方が子どもの成長を促すというものです。
たとえば、
今日は冷凍食品のおかずでもいい、
洗濯物をたたまずカゴに入れておく日があってもいい。
「完璧じゃなくても大丈夫!」そう思えるだけでも、ちょっと気持ちがラクになりますね。
👉あわせて読みたい「理想を手放すと育児がラクになる!」
「小さな幸せメモ」を書いてみる
疲れがたまると、どうしても「できなかったこと」「足りないこと」に目がいきがち。
そんなときこそ、ノートやスマホに「今日よかったこと・嬉しかったこと」を3つ書いてみましょう。
たとえば…
- 子どもが「ママありがとう」と言ってくれた
- 上司が「助かったよ」と声をかけてくれた
- コンビニの新作スイーツがおいしかった
こうした「小さな幸せ」を積み重ねていくと、何気ない日常にも幸福感を感じられ心の余裕にもつながります。
寝る前に書くと、「意外といいことあったんだな」と実感でき、気持ちよく1日を終えられておすすめです。
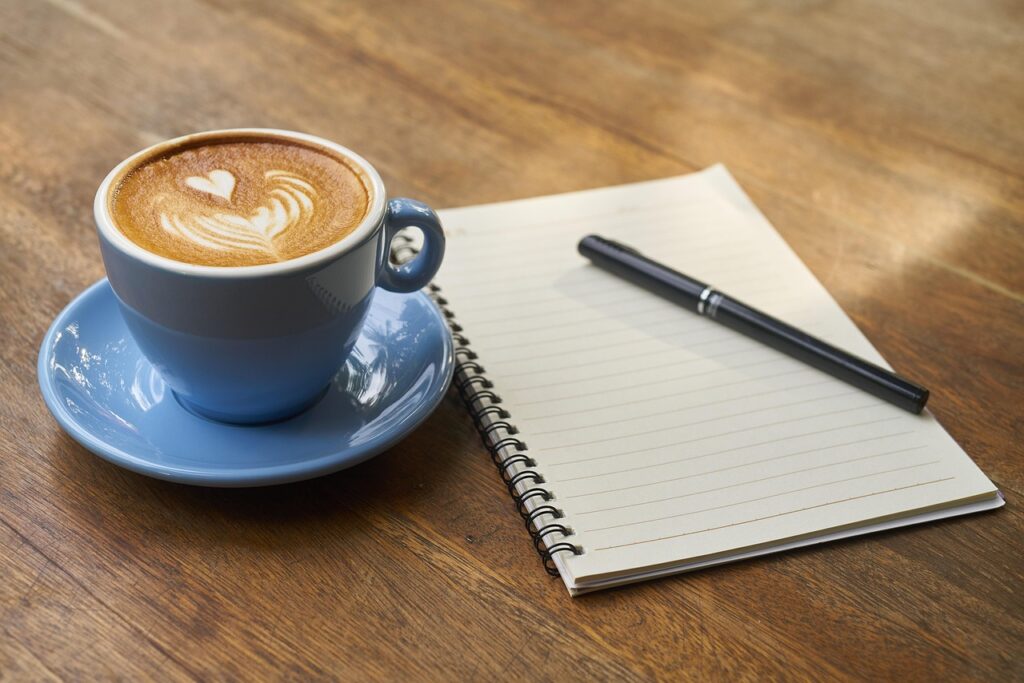
「1人だけのオアシス時間」を死守する
どんなに忙しくても、1日の中で「自分のための10分」を確保するのは超大事。
ここでポイントなのは「SNSチェック」や「家事の続き」ではなく、本当に心が休まることをする時間にすることです。
- 好きな音楽を聞く
- お気に入りの香りのアロマを焚く
- ノートに思ったことを数行書く
- ゆっくりマッサージをする
この短い時間があるかないかで、気持ちの回復度が大きく変わります。
「私にも大事な時間がある」と感じられることが、自己肯定感アップにもつながります
信頼できる人に「疲れた」と言ってみる
つい「私が頑張らなきゃ」と抱え込みがちですが、実は人に話すだけで心は軽くなります。
心理学の研究でも、ネガティブな気持ちを言語化することでストレスが軽減されたり、感情を落ち着かせる効果があるとされています。
夫や友達、ママ友、同僚など「安心して話せる人」を見つけて、
「今日疲れた〜」と口にするだけでも効果あり。
もし近くにそういう人がいなければ、日記アプリやSNSで匿名で吐き出すのも手です。
大切なのは「1人で抱え込まないこと」。
イライラもモヤモヤもため込まずに消化していきましょう。
🌈誰かに話すのが一番だけど、それが難しい日もありますよね。
そんなときのために、話すだけで気持ちを整理できるメンタルケアアプリもあります。👇
🌈同じママ同士で共感し合うのも効果あり。
Merci, Maman!(メルシーママン)は、ママ・プレママさんが妊娠・出産・育児にまつわる喜びや悩みなどを共感したり、子育てに関する様々な情報を知ることができる情報交流SNSです第3章:長く元気を保つ「習慣づくり」(長期ケア)
睡眠の質を上げる「夜のルーティン」
疲れを根本から回復させるには、やっぱり睡眠がカギ。
でも子どもの夜泣きや夜更かしで思うように眠れない日も多いですよね。
そんなときは「量より質」を意識。
- 寝る1時間前はスマホを見ない(ブルーライトは睡眠ホルモンを妨げる)
- 温かいお風呂に入った後、体温を下げながら眠気を誘う
- 部屋の照明をオレンジ色の間接照明にする
こうした小さな工夫で、深い眠りに入りやすくなるんです。
これで「寝たのに疲れが取れない」とはおさらばです。
栄養を「がんばらずに整える」
疲れは食事とも深く関わっています。
ただ、毎日バランスよく作るのは現実的に無理!だからこそ「がんばらない栄養管理」を取り入れましょう。
- 冷凍のカット野菜やミールキットを活用
- 食事作りをプロに外注
- たまには外食やお惣菜を買ってくる
「手抜きはサボり」ではなく、「効率よく進める工夫」なんです。
手作りじゃないご飯に罪悪感を感じる必要なんてありません。
使えるものはガンガン使っていきましょう。
🌈「ミールキットってこんなに楽なんだ」と実感。
働くあなたに簡単レシピでバランスごはんをお届け♪食材宅配のヨシケイ🌈ワーママの味方!宅配食
定期的に「ご褒美時間」を予定に組み込む
ママにとっての疲労ケアは、「回復」だけでなく「楽しみの前借り」も重要です。
月に1回でも、「美容院でヘッドスパ」「1人でカフェ」「推しのライブ配信を見る」など、ワクワクする予定をカレンダーに入れてみましょう。
「空いた時間にしよう」なんて思っていても、忙しいワーママにはそんな時間永遠に来ないことも。
あらかじめ予定の一つとして組み込んでおくのがポイントです。
心理学的にも、人は「楽しみを予定する」だけで幸福度が高まるとされています。
当日を迎える前から気分が上がり、「この日のために頑張ろう」と思える力になります。
「プロの力」を頼る勇気を持つ
どうしても疲れが抜けないときは、自分だけで解決しようとせず、専門家の力を借りるのも大事です。
- 医療機関での健康チェック
- 心理カウンセリング
- 家事代行サービス
「人に頼る=弱い」ではなく、「自分と家族を守るための選択」。
定期的にリセットする仕組みを持つことは、長く元気でいるために必要な投資です。
育児は長期戦。息切れしないことが大事です。
🌈30分単位で利用できて、交通費無料!依頼のハードル低めなのが◎
初回体験60分3,300円〜+【三菱地所の家事代行30min.】第4章:夫婦の協力と働き方の工夫(長期ケア)
家事分担を“見える化”
夫に「これやっといて」と言っても思うように伝わってない…
これは共働きママの“あるある”です。
こちらはお願いしたつもりでも、
夫にとっては「具体的に何をどこまですればいいの?」と不明確。
これがすれ違いの原因になります。
そして、「なんで頼んだのにやってないの!?」とケンカが勃発。
そこでおすすめなのが「家事分担表」を作ること。
冷蔵庫に貼ってもいいし、アプリで管理してもOK。
目的は、分担を明確化することです!
「誰が・いつ・何をやるか」を見える化するだけで、
「なんだか私ばっかり頑張ってない?」
「ワンオペ育児しんどいんだけど!?」
というイライラがグッと減ります。

我が家は、夫は帰りが遅いので平日は私が主に家事育児担当。
「平日は夫は頼りにできない」と割り切って、
中途半端に期待しないのでイライラもそんなにしません。
そのかわり、土日は家事育児は夫がメインで動いてもらうスタイル。
これで不公平感を軽減しています。
さらにちょっっとしたことでも「ありがとう」と伝え合う習慣を加えると、
家事が“チーム戦”に変わり、家庭内の空気も明るくなります。

「やめてもいい家事リスト」で体力温存
・毎日掃除機かける? → ロボット掃除機にお任せ!
・アイロンがけ? → 形状記憶シャツでカット!
・夕食? → 週に1日は「冷凍食品DAY」!
完璧を目指すほど、自分を追い詰めてしまいます。
だからこそ「やめる勇気」が大切。
全部自分でやる必要なんてありません。
最近では家事代行サービスや便利家電も進化しており、上手に使えば「家事に追われる日常」から解放されます。
「やめても困らない家事」をリスト化して、意識的に手を抜いてみましょう。
その余裕が、笑顔で家族に向き合うエネルギーにつながります。
👉あわせて読みたい「やめて正解だった」育児リストで心に余裕を作る!

実際私も、たまに家事代行にお掃除や食事作りをお願いしています。
最初は、「結構高額じゃない?なんだかもったいない」「贅沢かも」
と色々悩んでいましたが…
結果、「もっと早くにお願いすればよかった!」と、とても満足しています。
職場に相談する
「もう無理…」となる前に、勇気を出して職場に相談してみましょう。
企業には時短勤務・在宅ワーク・フレックスタイムなど、実は柔軟な制度が用意されている場合が多いのです。
けれど、制度は“待っているだけでは使えない”のが現実。
自分から声を上げることで初めて道が開けます。
また「仕事と家庭の両立に悩んでいる」と打ち明けること自体が、職場に理解を広げる一歩にもなります。
周囲も「そんな方法があったのか」と気づき、同じ立場の仲間が増えるかもしれません。
働き方は「選択肢がある」と知るだけでも気持ちが軽くなります。
自分のキャリアを定期的に見直す
「今の働き方、このままでいいのかな?」と立ち止まって考えるのも、とても大切なことです。
キャリアと家庭の両立には正解がありません。
ある時期は「子育て優先」、またある時期は「キャリアアップ優先」。
ライフステージに応じてベストな選択は変わっていきます。
ポイントは「他人と比べない」こと。
私はこれまで
・フルタイム正社員
・週3パート勤務
のどちらも経験していますが、
フルタイム正社員:パートや短時間勤務がうらやましくて仕方ない
短時間パート:バリバリ働き、キャリアアップしている同僚やママ友にモヤモヤ
結局、ほかの人と比べてもうらやましさや後悔ばかりがグルグル巡って、しんどいばかりでした。
「今の働き方は、私と家族に合っているか?」を軸に考える方が幸せを感じられます。
定期的に立ち止まることで、
「無理のない働き方」「納得できるキャリアプラン」を選びやすくなり、結果的に心のゆとりにつながると実感しています。

まとめ
疲れは「一気に消すもの」ではなく、「こまめにリフレッシュして、たまらないようにするもの」。
即効で効く小ワザから、心を整える中期ケア、長期的な習慣づくりまで、自分に合う方法を少しずつ試してみるのはいかがでしょうか。
そして何より大事なのは、「疲れた」と思う自分を責めないこと。
それはママとして弱いからではなく、毎日フル稼働で頑張っている証拠です。
今日からほんの5分でも、「自分のために休む」ことをやっていきましょう!
👉あわせて読みたい【毎日いっぱいいっぱい】ママの育児ストレス解消法まとめ
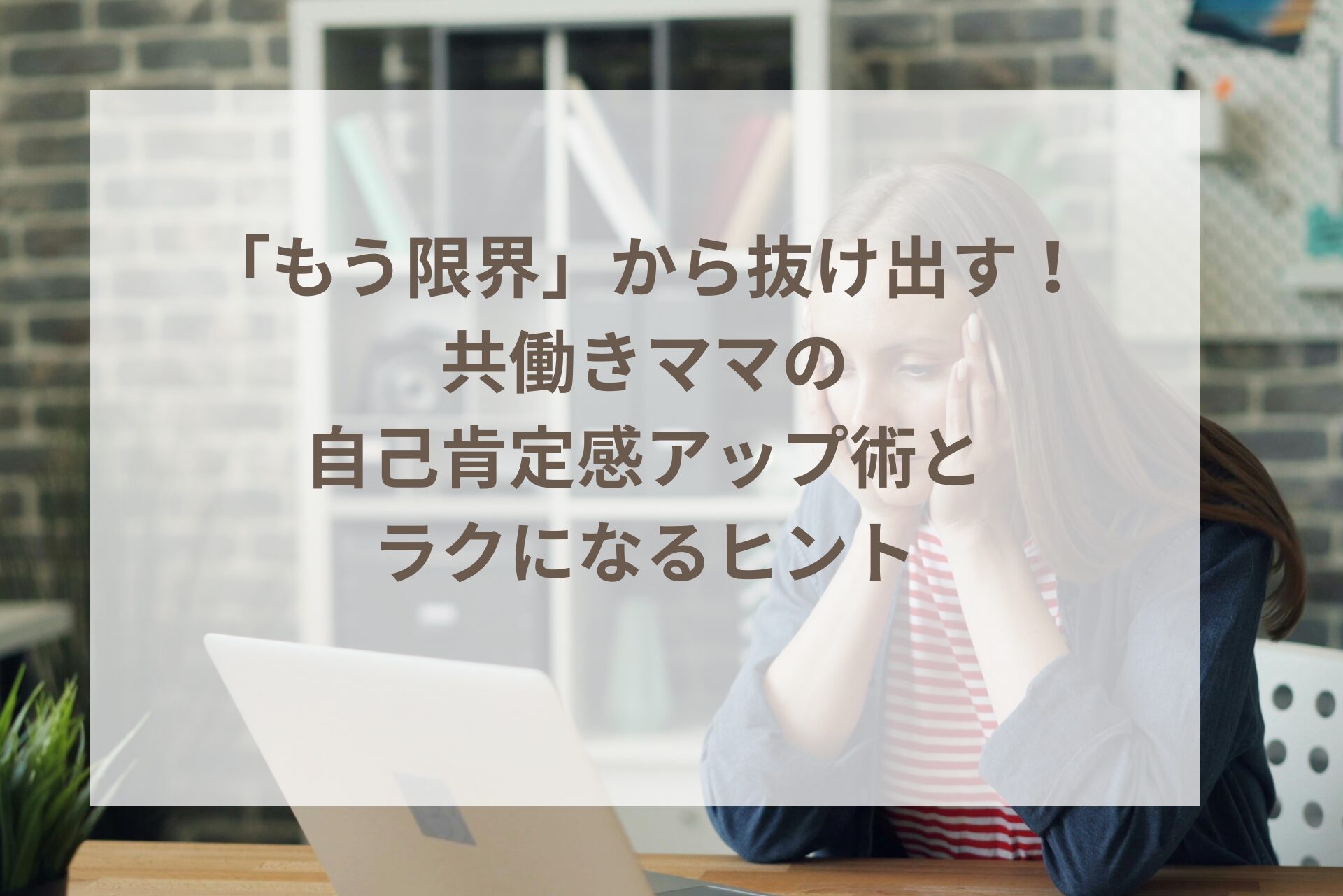



コメント